home>シスター三木の創作童話>犬になったおおかみ
シスター三木の創作童話
犬になったおおかみ

夜になって月が高くのぼりました。そして今まで暗かった森の梢と梢の間からさしこんでくる月の光が、あちらこちらに月の光の輪を落としていきました。そんなたくさんの光の中に、一匹の年よりおおかみがねそべっていました。おおかみは、ときどき頭をあげて月をながめています。
「そろそろ出かけるとするか」
おおかみは、ゆっくりと前足を起こし、それからお尻をあげて立ち上がりました。そして、月の光が作ったまだらもようの道を通って村が見える丘の上に出ました。おおかみは、またそこでねそべりました。しかしこんどは、下に見える村から目を離しません。じーっとにらんでいます。
「もう、いいようだな」
年よりおおかみはそういうと、急にすばしっこくなって頭を低く下げ、地面をはうようにして丘のスロープを下りていきました。村の家に近づくにつれて、年よりおおかみは、若いおおかみのように身軽になりました。すーっ、すーっすーっと、こちらの家からあちらの家へとわたっていきます。月は、そんなおおかみをじっと照らしていました。おおかみが最後に足をとめたのは、一軒のにわとり小屋の前でした。おおかみは、しずかに後足でにわとり小屋の地面をけって穴を堀りはじめました。目はするどく左右を見て何かを警戒しています。おおかみがけあげた土が、にわとり小屋にとび散りました。止まり木の上でぐっすりねむっていたにわとりたちは、明るい月の光にだまされて、もうお昼ごろなんだと思ってしまったようです。それに、パチパチと音をたてて土がとびこんできたので、くいしんぼうのにわとりたちは、えさがまかれたのだと、すっかり感ちがいしてしまったのです。そしておおかみが堀った穴をめがけて、いっせいに止まり木からとびおりてきました。おおかみは、そこをねらっていたのです。
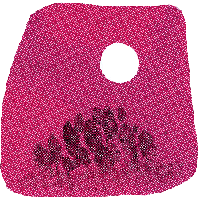
月の光の中を黒いかたまりが走りぬけていきました。そのあとに、白い羽根がふわふわと、とび散って残りました。おおかみは、こうして毎晩のように村人のにわとり小屋をおそっていたのでした。森の中で舌なめずりをしながら、おおかみはいいました。
「おれさまも、生きているかぎり喰う権利がある。人間だってにわとりを喰っているじゃないか。同じことなんだ。この森の中じゃ、おれさまのようなおいぼれに、つかまるような、間ぬけの動物は一匹もいない。人間さまんちのが、いちばんいただきやすいってもんさ」
おおかみは、また舌なめずりをして、口ひげのまわりについていたにわとりの血を、赤くて長い舌でペロリとなめました。
このおおかみは、村人たちから、とても恐れられていました。もうこれまでに何十羽ものにわとりが、このおおかみから殺され盗まれていたのです。そこで村人たちは、このにくらしいおおかみ狩を計画しているところでした。
ちょうどそこへ、村人たちから聖人さまと尊敬されているフランシスコという人がやってきたのです。村人の話を聞くとフランシスコは、
「わたしが、そのおおかみにあいにいきましょう」
と言って、村の人たちがとめるのも聞かず、おおかみのいる森の方へいってしまいました。
そして、この年よりおおかみとあったのでした。
おおかみは、今にもとびかからんばかりに、後足をけって歯をむき出し、低いうなり声をあげています。ところがフランシスコの方は、両手を広げて、友だちを迎える時のように、ほほえんで立っているだけなのです。おおかみは、何だか、ひょうしぬけがしてきました。それに年よりなのでつかれてしまったのです。

それから、どのくらいたったのでしょうか。フランシスコとならんで歩いていく一匹の犬のかげが、丘のスロープに長くのびていました。
フランシスコと出会ったおおかみは、どうしたわけか、いつのまにかおとなしい犬のようになっていたのでした。

 トップページへ
トップページへ